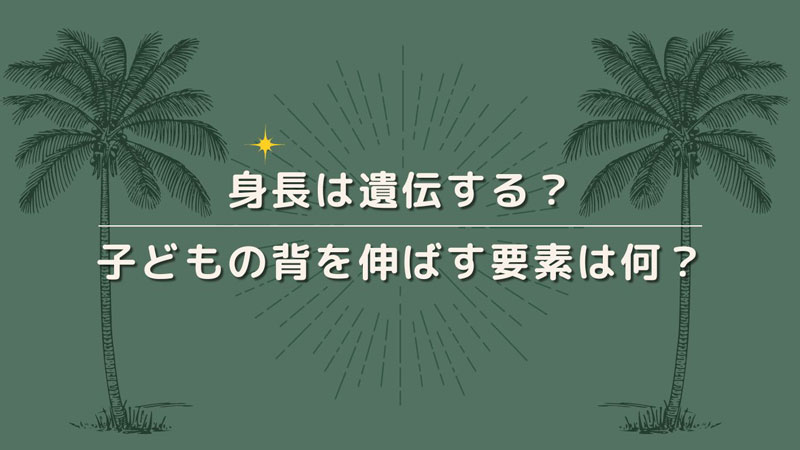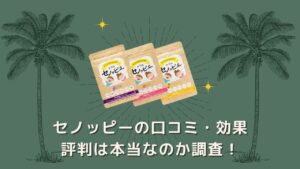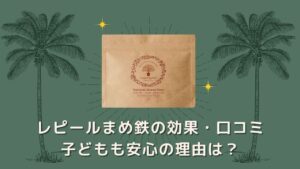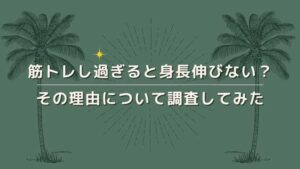身長が高い子供になって欲しいと思う方も多いですが、子供の成長過程では遺伝が重要になり、その他遺伝だけではなく、他の要因が重なることもあります。
ここでは、子供の身長のために、大切な成長期をどう過ごせばいいかわかるように解説していきます。
子供の身長は遺伝が大きな影響を及ぼす
身長はすべてが遺伝で決まるわけではありません。
身長を伸ばすためには遺伝だけではなく、日々の生活習慣なども関わってきます。
ここでは、そんな成長期である子どもの身長を伸ばすために影響を及ぼすことを解説していきましょう。
母親からの遺伝が大きいといわれている
子供の身長は父親よりも母親の遺伝の影響を受けやすいという結論が出ています。2007年の城西大学研究年報には身長における子供と親の性別ごとの相関を統計で調べた結果が次のように出ています。
母ー息子間の相関係数0.45は父ー息子間の0.34より高く、母娘間の相関係数0.34も父娘間の0.32より高くなった。このことは表面的に身長において父親より母親の影響が高いことを示している。
https://libir.josai.ac.jp/il/user_contents/02/G0000284repository/pdf/JOS-KJ00004569848.pdf
また、それより前にも、身長における男女別親子の相関関係についての研究結果が発表されています。1988年の昭和医学会雑誌にも次のように書かれています。
男子の身長,骨盤発育は若干両親の影響を受けるにすぎないが、女子では身長・骨盤ともにその発育は両親の身長に強く影響され、しかも骨盤発育は初経発来周辺期に当たる思春期前半は母の身長因子が影響するが、思春期後半は父の身長因子の影響も出てくることが示唆され、きわめて興味ある結果であった。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsma1939/48/2/48_2_215/_pdf
過去2つの論文からみて、身長は母親の遺伝が強いと考えることができます。
必ずしも遺伝で全てが決まるわけではない
身長は90%が遺伝と言われており、たしかに両親の身長と子供の身長に関係はあります。両親とも身長が低いという場合に、子供がどれくらい身長が伸びるか予測すると、確率では平均身長を超える可能性は低いということになります。
両親の身長を使って子供の最終的な身長を予測する計算式があります。日本体育協会が出しているもので、この計算式で求められる数字は目標身長と言われています。
- 男子の場合(父の身長+母の身長+13・0)÷2 + 2・0
- 女子の場合(父の身長+母の身長-13・0)÷2 + 2・0
となります。
しかし、これはあくまで予測される身長の平均値です。この数値よりも低くなることもあれば、高くなることもあります。
必ずしもこの例に当てはまるというわけでもなく、遺伝が全てというわけでもありません。
もし両親とも身長が低い場合であっても、子供が平均より高くなる可能性もあります。
それは成長期の過ごし方や、食事などでも変わってくるということです。次に成長期の過ごし方が大事であることを解説していきましょう。
身長が決まる要素で遺伝以外に大事なことって?
身長が決まる要素で遺伝子以外に大事なことは成長期の過ごし方です。
一般的に日本人における成長のピークは平均値として男子が13歳、女子が11歳といわれています。個人差はあり一概にこれが全員に当てはまるとはいえません。
高校生になって急に身長が伸びる子もいれば、小学校高学年で成長期の最盛期を迎える子もいます。
つまり、暦上の年齢は成長と比例しないことがわかります。身長を伸ばす可能性を高めるために必要なことは、体の年齢を見極めることでもあります。
例えば日常生活の中で、スポーツをしている子どもとそうでない子どもでも差が出ます。スポーツをしている子どもは一般的な同世代の子どもに比べ、エネルギー消費が1.2〜1.5倍必要だと言われています。
一般的に成長期といわれる12〜17歳の子どもの1日摂取カロリーは約3000kcalです。取り入れた栄養素はまず疲労回復に使われます。摂取カロリーが不足していれば、怪我をしやすくなることなども考えられます。
子どもの日常生活の中で、成長期をどう過ごしているかによっても身長の伸び方が変わります。身長を伸ばすために、成長期の大切な3つのポイントを理解して取り組むのがいいでしょう。
身長を伸ばすために大事な成長期の3つのポイント
身長を伸ばすためには、成長期にしなくてはいけない大切な3つのポイントがあります。ここではその3つのポイントについて解説していきましょう。
また、身長を伸ばす方法について、別のページでかなり詳細に解説しています。こちらの記事もぜひ参考にしてください。

栄養バランスのいい食事をする
身長を伸ばす過程、成長のためにはカルシウムやタンパク質・ビタミンなど栄養バランスのいい食事をすることが大切です。
特に骨の形成に関わるビタミン・カルシウム、筋肉を作ることに大切なたんぱく質・ビタミン・ミネラルなども重要です。
例えば、ビタミンDはカルシウムの吸収を助けてくれる働きをし、ビタミンKはカルシウムの沈着を助けることで骨を丈夫にします。
また、アミノ酸は脳下垂体を刺激して成長ホルモンの分泌を促す働きをします。
これらのビタミンやアミノ酸が不足すると、代謝がスムーズにおこなえなくなるため、毎日の食事に意識的に入れましょう。
背を伸ばす食べ物などもあると思いますが、決まった食品だけを食べるのではなく、栄養バランスのいい食事をすることが大切です。
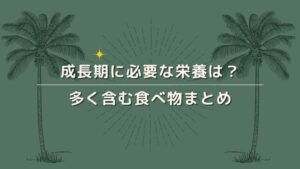
しかし、毎日の食事だけでバランスよく栄養を摂取するのはとても大変です。
また、食品から摂取するには含有量が少なく、効率よく栄養素が摂れない場合もあります。
そんなときは、背が伸びるサプリなどを利用するのも効率的な方法です。普段の食事と合わせて利用すれば、成長期にしっかりと栄養補給ができます。

おすすめの栄養サポートサプリ
規則正しい生活をする
規則正しい生活は健康管理の基本となりますが、中でも大事なのが睡眠時間です。成長ホルモンが盛んなのは、深い睡眠のときです。
特に眠りについたあとのレム睡眠(深い眠り)で成長ホルモンの分泌が盛んに行われるため、非常に大切といわれています。
寝る時間も大切ですが眠りの深さも大切です。
深い眠りのためには日中しっかりと体を動かすことが必要になります。できるだけ運動をさせたり、部活などを取り入れてあげるだけで、新陳代謝の向上により成長ホルモンに大きく働きかけます。
また、朝日を浴びて14〜16時間後に眠気を誘発するメラトニンというホルモンが分泌されます。
朝起きる時間にも気をつけるようにするといいでしょう。
メラトニンは周囲が明るいとうまく分泌されないので、ベッドに入る1〜2時間前に間接照明を使った部屋で過ごすようにするとメラトニンの分泌を促せます。
スマートフォンやタブレットなどは深い眠りを妨げるので、眠る前の使用には注意が必要です。
怪我をしない
成長期に大切なポイントとして怪我をしないようにすることが挙げられます。
成長期の痛みとして、「成長痛」があります。成長期の子供は特別な原因がないにも関わらず痛みが生じる状態で、夕方から夜間に痛みが生じることが多く、朝には何もなかったように痛みがなくなることが多いです。
つまり、筋肉、関節、骨などには異常がないということです。
しかし、異常がある場合は「成長痛」とは呼ばず、怪我の分類におかれます。例えば、骨端線が痛くなる骨端症が代表的なものです。成長期は、筋肉の伸びが骨の成長より遅いため、筋肉が骨についている部位を引っぱるような状態になり痛みが生じます。
筋肉が骨についている部分は、成長軟骨板という組織でできており、骨を増殖しながら大きくする部分で、レントゲン上では骨端線と呼んでいます。骨端線には、新しく骨になるための「成長軟骨」と「骨端核」とよばれる部分が存在し、骨の強度が弱いです。
この時期に激しいスポーツなどで、使いすぎによるストレスが、痛みや成長障害を起こすことがあります。こういった場合はきちんと整形外科で受診をし、治療するようにしましょう。
また、こういった症状に見舞われないためにも、激しすぎる運動などで怪我を繰り返すことで身長の成長を妨げることもあります。怪我をしないことは成長に欠かせないことです。
身長と遺伝についてのよくある質問
今回は身長と遺伝について解説してきましたが、ここではよくある質問を紹介していきましょう。
- 両親が共に高身長なら子供も高身長になりますか?
-
両親が共に高身長なら子どもも高身長になるかといわれると、答えは必ずしもそうではありません。両親が高身長でも、両親が低身長でも背が高い・低いということはあります。また、後天的な考え方でいうと、特定の栄養素が非常に欠乏してる・思春期早発症によって身長の伸びが悪くなったということも考えられます。
- 遺伝の影響は何パーセントくらいあるのでしょうか?
-
身長は90%が遺伝で決まると言われています。詳しくは、 (h3 必ずしも遺伝で全てが決まるわけではない)で記載しているのでご覧ください。